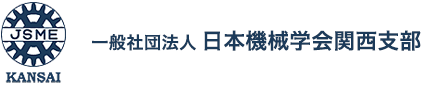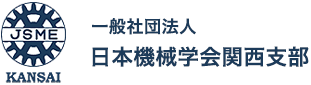| (社)日本機械学会関西支部 | 2010.3.19更新 |
| 平成21年度関西学生会学生員卒業研究発表講演会BPA受賞者一覧(2010 3/15) | ||
| 2010年3月15日に神戸大学で開催された平成21年度関西学生会学生員卒業研究発表講演会では、 422件の発表があり、このうち40件がBPA(Best Presentation Awards)受賞しました。 以下にBPA受賞者一覧を記して、その栄誉を称えます。 |
| 午前の部 |
| 室 | 講演番号 | タイトル | 氏名 | 所属 |
| 1 | 106 | 数値流体力学解析による医療用フィルターのデザインの評価 | 滝本 遥 | 大阪大学 |
| 2 | 201 | マウス左心室用硬さセンシングシステムの開発 | マイケル ティオン ホー ヒー | 大阪大学 |
| 3 | 311 | カーボンナノチューブによるタンパク質分子の部位特異的捕捉と分子間相互作用力の計測 | 山口 圓 | 大阪大学 |
| 4 | 407 | 蚊の羽ばたき飛行の機構解明のための実形状拡大弾性翼モデルの作製 | 細野真司 | 関西大学 |
| 5 | 509 | 湿潤環境下における微細粒鋼の回転曲げ疲労強度におよぼす結晶粒径の影響 | 廣田 剛 | 舞鶴高専 |
| 6 | 610 | 超弾性材料を用いた磁気駆動トルクアクチュエータにおけるヨーク形状の検討 | 倉田裕二 | 兵庫県立大学 |
| 7 | 710 | 樹脂表面への無電解重合によるポリピロール膜の形成 | 花山由宇 | 和歌山大学 |
| 8 | 805 | 傾斜機能超硬合金金型における硬さ分布および残留応力の制御 | 井上恵太 | 大阪大学 |
| 9 | 906 | カーボンナノチューブの通電加工時の温度計測 | 板谷翔太郎 | 大阪大学 |
| 10 | 1006 | 高乱流場におけるフィルム冷却の混合現象解明に関する研究 | 西垣丈史 | 大阪大学 |
| 11 | 1108 | 周方向グルーブを用いたインデューサに生じるキャビテーション不安定現象の抑制に関する実験 | 青野 淳 | 大阪大学 |
| 12 | 1209 | バルブ機構に着目した振動流血液ポンプの小型化 | 生原尚季 | 大阪大学 |
| 13 | 1309 | 弱い衝撃波により誘起される境界層に関する研究 | 長尾哲史 | 大阪大学 |
| 14 | 1406 | 高圧純酸素火炎を用いた粒子球状化技術に関する研究 | 鈴木信吾 | 大阪大学 |
| 15 | 1510 | 剥離・再付着乱流に対応した壁関数乱流モデルに関する研究 | 石橋 優 | 大阪府立大学 |
| 16 | 1608 | セラミックスハニカムを用いた熱再生による燃料改質器性能への影響 | 川邉将史 | 京都大学 |
| 17 | 1705 | Hamilton-Jacobi方程式の一近似解法 | 尾崎友彰 | 大阪府立大学 |
| 18 | 1806 | 高減衰転がり免震装置の開発の研究 | 田口ジェレミー | 大阪府立大学 |
| 19 | 1906 | 水酸化フラーレンの温度依存特性評価に基づくナノCMPメカニズムの検証 | 鹿野和昌 | 大阪大学 |
| 20 | 2003 | 4脚歩行ロボットの不整地踏破スキルの抽出 | 三好敦士 | 和歌山大学 |
| 午後の部 |
| 室 | 講演番号 | タイトル | 氏名 | 所属 |
| 1 | 122 | 不規則欠陥理論の構成式に基づくZr基金属ガラスの大変形有限要素解析 | 山口恭平 | 大阪大学 |
| 2 | 216 | 選択的な状態遷移によって生み出される多分子モーターの運動機構の基礎的検討 | 國枝直弘 | 大阪大学 |
| 3 | 320 | プリン体の簡易検出法の開発に関する基礎研究 | 藤田一馬 | 舞鶴高専 |
| 4 | 417 | 第二次高調波顕微鏡を用いた光学的熱傷診断に関する基礎研究 | 田仲亮介 | 大阪大学 |
| 5 | 522 | Zr基バルク金属ガラスの繰返しせん断応力下の疲労 | 三上恒平 | 神戸大学 |
| 6 | 617 | 微細セルロースを由来とする炭化繊維を添加したカーボン/カーボン複合材料の機械的特性 | 堤 博利 | 同志社大学 |
| 7 | 718 | 砂への高速貫入特性に及ぼす衝突速度の影響 | 福間俊吾 | 大阪大学 |
| 8 | 718 | 高速双ロールキャスティングによる5182合金薄板の内部欠陥の改善の検討 | 塩津悠介 | 大阪工業大学 |
| 9 | 921 | ディスクブレーキの鳴き振動モードに及ぼす摩擦接触部の面圧の影響 | 山田雄亮 | 滋賀県立大学 |
| 10 | 1017 | マイクロ流路を用いた繊維間樹脂流動の実験モデル構築 | 密山泰用 | 京都大学 |
| 11 | 1122 | ムービングベルトの試作と車両の揚抗力測定について | 森田晃佳 | 大阪工業大学 |
| 12 | 1221 | 離散要素法によるブルドーザ押し土シミュレーション | 中川裕太 | 大阪大学 |
| 13 | 1318 | ディーゼル排ガス中の粒子状物質の触媒付着 | 粟田和輝 | 神戸大学 |
| 14 | 1418 | 二酸化炭素の水平細管内の流動様式 | 藤本集平 | 関西大学 |
| 15 | 1513 | 半炭化圧密バイオ固体燃料に関する研究 | 市野善三 | 近畿大学 |
| 16 | 1614 | 燃料電池用小型空気ターボブロワの開発 | 中島健賀 | 兵庫県立大学 |
| 17 | 1715 | 分散制御による多自由度振動系の共振点駆動(固有振動を利用した4足歩行の歩容の実現) | 平塚智裕 | 滋賀県立大学 |
| 18 | 1817 | 機械設計における自己組織化マップを用いた創造的部品構成法の研究 | 仲地将志 | 神戸大学 |
| 19 | 1918 | ニュートラルステア特性および横滑り零化の同時実現に関する一考察 | 中 将之 | 大阪府立大学 |
| 20 | 2016 | マルチ駆動リニアモータを用いたバック転・パラレルリンク機構の設計 | 打越友哉 | 近畿大学 |
| 関西学生会では、Best Presentation Awards(BPA)を設けて、学生員卒業研究発表講演会において素晴らしい口頭発表を行った学生員の栄誉を称えている。これは、わが国におけるプレゼンテーション能力の欠如が叫ばれる中で、その養成を目的にして1998年に制定されたものである。プレゼンテーションの評価は座長(大学院生)とコメンテータをお願いしている支部商議員および会員校の先生方計3名によって行われている。 以下にBPAに関する審査方法などを参考として記す。 | |||
| ・ | BPA受賞者選定 | 各講演室、午前または午後の連続した2セッション毎にBPA受賞者を選定する。 (講演が18室の場合は、18×2=36名) |
|
| ・ | 審査方法 | 午前または午後の連続した2セッションの各講演について、BPA受賞者選定のための採点 を行う。 当該2セッションを通じ、最高得点者をその2セッションにおけるBPA受賞者とする。 |
|
| ・ | 表 彰 | 賞状および副賞(記念メダル)を贈呈、また受賞者名を会誌、支部HPおよび翌年度発行の機関誌春秋に掲載する。 | |
 |
||
| BPA記念メダル | ||